
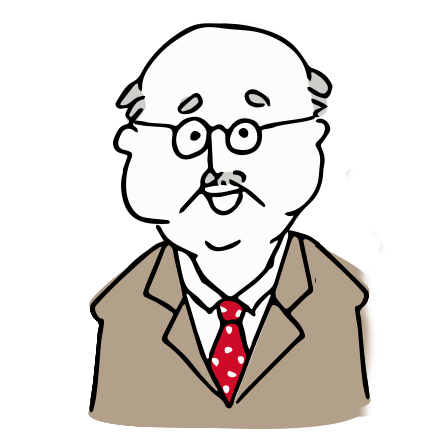
Amazfitのスマートウォッチが気になりますね。
特に、コスパの良さそうな「Amazfit band 7」。
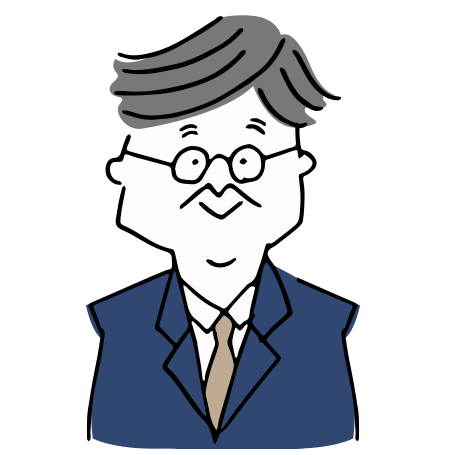
良い製品に目をつけましたね。
画面も見やすくてとてもいいスマートウォッチです。
使用感や気になるポイントを詳細にレビューしますよ!
Amazfitは、2015年にZepp Healthというメーカーから登場したスマートウォッチのブランド。
そのコスパの良さから、世界中で着実にシェアを伸ばし続けています。
今回は、Amazfitブランドのスマートウォッチの中でも特にコスパの高いモデル、
「Amazfit band 7」をレビューします。
搭載されている機能だけでなく、実際に使用する中で気づいたことや、競合製品との比較まで。
良い点だけでなく、気になった点も含めて辛口にレビューしました!
購入を悩んでいる方の疑問を解消できれば幸いです。
先に結論だけお伝えすると、用途がマッチするなら買いの一本です。
Amazfit band 7 について

Amazfitのスマートウォッチには、現在5つのシリーズがあります。
- Bandシリーズ
- Bipシリーズ
- GTRシリーズ
- GTSシリーズ
- T-Rexシリーズ
Bandシリーズ(左)とBipシリーズ(右)はエントリーモデルとして販売されています。
お手頃な価格で、Amazfitのスマートウォッチの中でも特に人気が高い機種。
丸い文字盤が目を引くGTRシリーズ(左)と高級感のあるGTSシリーズ(右)は、
ファッショナブルなラインナップ。
フォーマルからカジュアルまで、しっかり活躍してくれるモデルです。

そしてスポーツ向けのタフなモデルがT-Rexシリーズ。
頑丈なボディと無骨なデザインが魅力的です。
アウトドアでガシガシ使いたいならT-Rexですね。
この通り、人気のブランドなだけあって様々なモデルがラインナップされています。
今回紹介するBandシリーズはエントリーモデルとはいえ、他のモデルに引けを取りません。
機能も十分で、コスパという観点では最もおすすめできるモデルです。
それでは、魅力的だと感じた部分や、使用していて気になったポイントをみていきましょう。
Amazfit band 7 の魅力的なポイント
Amazfit band 7 は最新のスマートウォッチ。
前のバージョンであるAmazfit band 5 から大きく進化しています。
過去のモデルでは評判の良くなかった部分を改善したり、さらに使いやすくアップデートが重ねられてきました。
そんなAmazfit band 7 には、魅力的なポイントが沢山!
例えば、
- 本体が軽い
- ディスプレイが大きくて見やすい
- 電池持ちが良い
- 本体で細かい設定が可能
- 健康管理用の機能が豊富
- スポーツ向けの機能が豊富
- Alexaに対応(スマートホームデバイスとも連携可)
- アプリがインストールできる
などなど。
それぞれ詳しくご紹介していきましょう。
本体が軽い
Amazfit band 7 の重さはなんと28g。
Amazfitのラインナップの中でも最軽量となっています。
つけているのを忘れてしまうほど軽いので、一日中つけていても気になりません。
健康管理のため、寝ているときも装着するなら大きなメリットですね。
ランニングなどの運動の記録を取るときも、軽いスマートウォッチなら邪魔にならず快適です。
ディスプレイが大きくて見やすい
Amazfit band 7 では、1.47インチの有機ELディスプレイが使われています。
表示部分が大きいと文字やアイコンが見やすく、操作性も高いですね。
有機ELディスプレイは、ハイエンドモデルのスマートフォンなどに使われています。
従来の液晶ディスプレイよりも、鮮やかに表示できるのが特徴。
有機ELは液晶より高速に表示ができるので、動きがサクサクになるというメリットも。
また、Amazfit band 5 よりも画面が大きくなったことで、スマートウォッチ本体からできることが増えました。
例えばアラームの設定。
前モデルでは、専用のスマホアプリからアラームの設定をする必要がありました。
Amazfit band 7 なら、スマートウォッチ単体でアラームの新規設定をすることが可能。
操作性が高いだけでなく、できることが増えたというのは嬉しいポイントです。
電池持ちが良い
様々な機能が搭載されているAmazfit band 7 ですが、以前のモデルから進化したのは、機能だけではありません。
バッテリーの持ちも、若干ですが改善されました。
前モデル、Amazfit band 5 のバッテリー持ちは、通常使用で15日間(公式サイトでの公称値)でした。
Amazfit band 7 では最大18日間となっており、2割ほどバッテリー性能がアップしています。
実際に使用している感じでは、バッテリーのことは気にせずにSNSの通知やアラーム等を普通に使って、10日以上は充電が持ちます。
充電自体もマグネットのケーブルを接続するだけなので手軽ですね。

お風呂に入るタイミングにでも充電しておけば、
「気づいたらバッテリーが切れていた」という状況にはならないでしょう。
画面が大きくなって消費電力も多いはずなのに、バッテリーの持ちが良くなった。
メーカーの技術力の高さを実感します。
本体で細かく設定が可能
ディスプレイのところでもお話しましたが、Amazfit band 7 は本体画面から細かく設定が可能です。
アラームだけではなく、画面の明るさや常時オンの設定・睡眠関連の設定まで、スマートウォッチ単体で変更可能。
スマートフォンを出さずに色々と設定ができるのは本当に便利です。
寝る前にアラームの設定を修正したいときでも、サクッと済ませることができますよ。
健康管理用の機能が豊富
スマートウォッチの機能の中でも外せないのが、健康管理の機能。
Amazfitのスマートウォッチでは、健康に関する面白い指標がチェックできます。
その名も「PAI」。
パーソナルアクティビティインテリジェンスという言葉の略です。
PAIは、心拍数に基づいて算出されるスコア。
運動をして心拍数が上がると、PAIスコアがどんどん増えていきます。
直近1週間の合計PAIスコアが100を超えると健康的とされています。
Amazfit band 7 では、このPAIスコアを簡単にチェックすることが可能。
私もリモートワークがメインなので運動不足ですが、PAIスコアを確認するたびに「対策を取らねば」という気持ちになります。。
歩いた歩数や睡眠の状態なども、詳細なデータを取ってくれています。
睡眠の質が良くなかったときは、寝る前の行動を見直すきっかけにもなりますね。
スポーツ向けの機能が豊富
記録を取れるのは普段の生活の中だけではありません。
スマートウォッチから、120種類以上のスポーツの活動記録を取ることができます。
すべての機能を使おうと思ったら大変ですね。
また、PeakBeatsというアルゴリズムを搭載しており、運動による体への負荷や効果を確認することができます。
あまり馴染みのないワードかもしれませんが、EPOC・最大酸素摂取量・回復時間などが測定可能。
EPOCは、日本語に訳すと運動後過剰酸素消費。
負荷のかかる運動を行ったあとは、体は酸素が足りていない状態になります。
その足りていない酸素を、運動後に体が摂取するのがEPOC。
EPOC、つまり運動後に酸素を取り込むときには、カロリーが消費されます。
これがいわゆるアフターバーン効果ですね。
ダイエットでも重要な指標です。
日々の運動の記録を細かく分析して効果をチェックする、という使い方にもピッタリですね。
Alexaに対応(スマートホームデバイスとも連携可)
Amazfit band 7 は本体にマイクも内蔵しており、Alexaにも対応。
対応している製品と組み合わせることで、ほとんどの家電がスマートウォッチから操作できるようになります。
就寝時や起床時に、テレビ・エアコン・照明を布団の中から操作できるのはとても快適ですよ。
Zepp OS搭載でアプリのインストールが可能
Amazfit製品を手にする前、ずっと気になっていたのが搭載されている Zepp OS。
スマートウォッチのOSといえば、
- アップルウォッチのWatch OS
- Googleが開発しているWear OS
が有名ですね。
上記のOSが搭載されていると、スマートウォッチ用のアプリを本体にインストール可能。
使い方に合わせて機能を増やすことができるので、活用の幅が広がります。
アプリがインストール可能なスマートウォッチは、数万円以上のものがほとんど。
ですがAmazfit band 7 はなんと、1万円以下で購入可能です。
OS搭載のスマートウォッチを安く試したいのなら、Amazfit band 7 一択ですね!
人によってはイマイチ?デメリット3つ
多くのメリットを紹介してきましたが、物足りないと感じた部分もいくつかあります。
検討する際に注意すべきポイントは、
- 以前のモデルに比べると装着感が強い
- ディスプレイを常時点灯していると電池がすぐに減る
- Wear OS搭載モデルよりも使えるアプリが少ない
の3つ。
順番にみていきましょう。
以前のモデルに比べると装着感が強い
前のモデルであるband 5(左)に比べ、band 7(右)は本体が一回り大きくなっています。
band 5 は本体がバンド部分とほぼ同じ太さ。
そのため、装着感をほとんど感じませんでした。
対してband 7 では、手首を動かしたときに若干ですが装着感があります。
不快なわけではありませんが、手首を頻繁に動かすスポーツ等では気になるかもしれません。
画面の見やすさや操作性とトレードオフですね。
ディスプレイを常時点灯していると電池の減りが速い
今までのスマートウォッチは、基本的には画面が消えており、画面に触れるか本体を傾けることで画面が表示される製品がほとんどでした。
しかし、最近は常に画面を点灯させることができるスマートウォッチが登場しています。
Amazfitのスマートウォッチも、常に画面をさせることが可能。
ですがもちろん、画面を常時点灯しているとバッテリーの消費が激しくなります。
体感では、通常の倍くらいのスピードでバッテリーが減っていきます。
とはいえ、画面が常時点灯する機能は人気の機能。
将来的には技術の進歩で、常時点灯しているのが当たり前の時代が来るかもしれません。
今後にも期待です!
Wear OS搭載モデルよりも使えるアプリが少ない
Zepp OSを搭載していて、好きなアプリをインストールできるのはメリットとお伝えしました。
ですが1つ注意点があります。
Zepp OSでインストールできるアプリは10数個程度。
アップルウォッチのWatch OSのように、よりどりみどりという訳ではありません。
おそらくインストール可能なアプリは、今後増えていくはず。
こちらも楽しみにしておきましょう。
競合製品?「Xiaomi Smart Band」と比較してみた

Amazfitの競合製品として、真っ先に挙げられるのが Xiaomi の Smart Band(写真右)。
お互いの製品を意識しているのか、スペックもかなり似通っています。
大きな違いとしては、製品の外観。
Xiaomi の Smart Band は、Amazfit Band 5(前モデル)のようなデザイン。
Amazfit の方が、画面が見やすく操作性も高いので、一歩先を行っている感じです。
また、Xiaomi Smart Band は本体にアプリを追加することはできません。
アプリをインストールしてカスタマイズできるという点では、Amazfit に軍配が上がります。
好みの問題ですが、この2つで悩むのなら、総合的に見て Amazfit がおすすめですね。
まとめ
Amazfit band 7 について、魅力的なところから気になる部分まで含め、ご紹介してきました。
基本的な機能はしっかり揃っていて、本体にアプリまでインストールできる。
それでいて数千円台で購入できるという、コスパに優れた一本です。
初めてのスマートウォッチにも良し、プレゼントとして贈るも良し。
どんな方にもおすすめできるオールマイティな製品なので、気になっているならぜひお試しあれ!
Amazfitの他の製品が気になるなら、こちらの記事もどうぞ↓↓
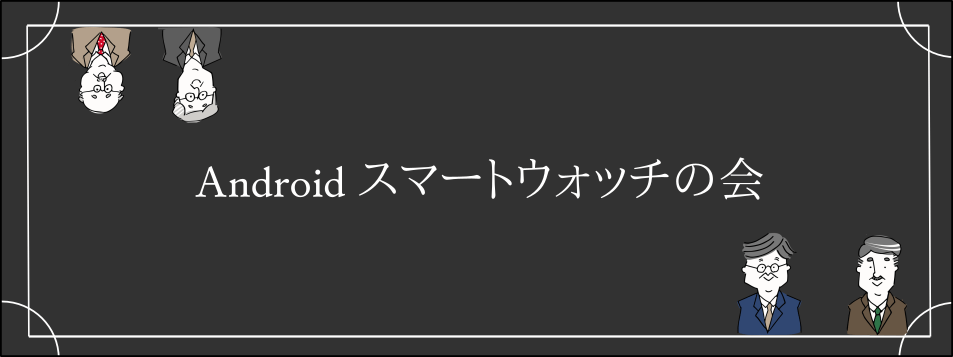


















コメント